【未来を創る人事のリレートーク】人材開発と越境研修
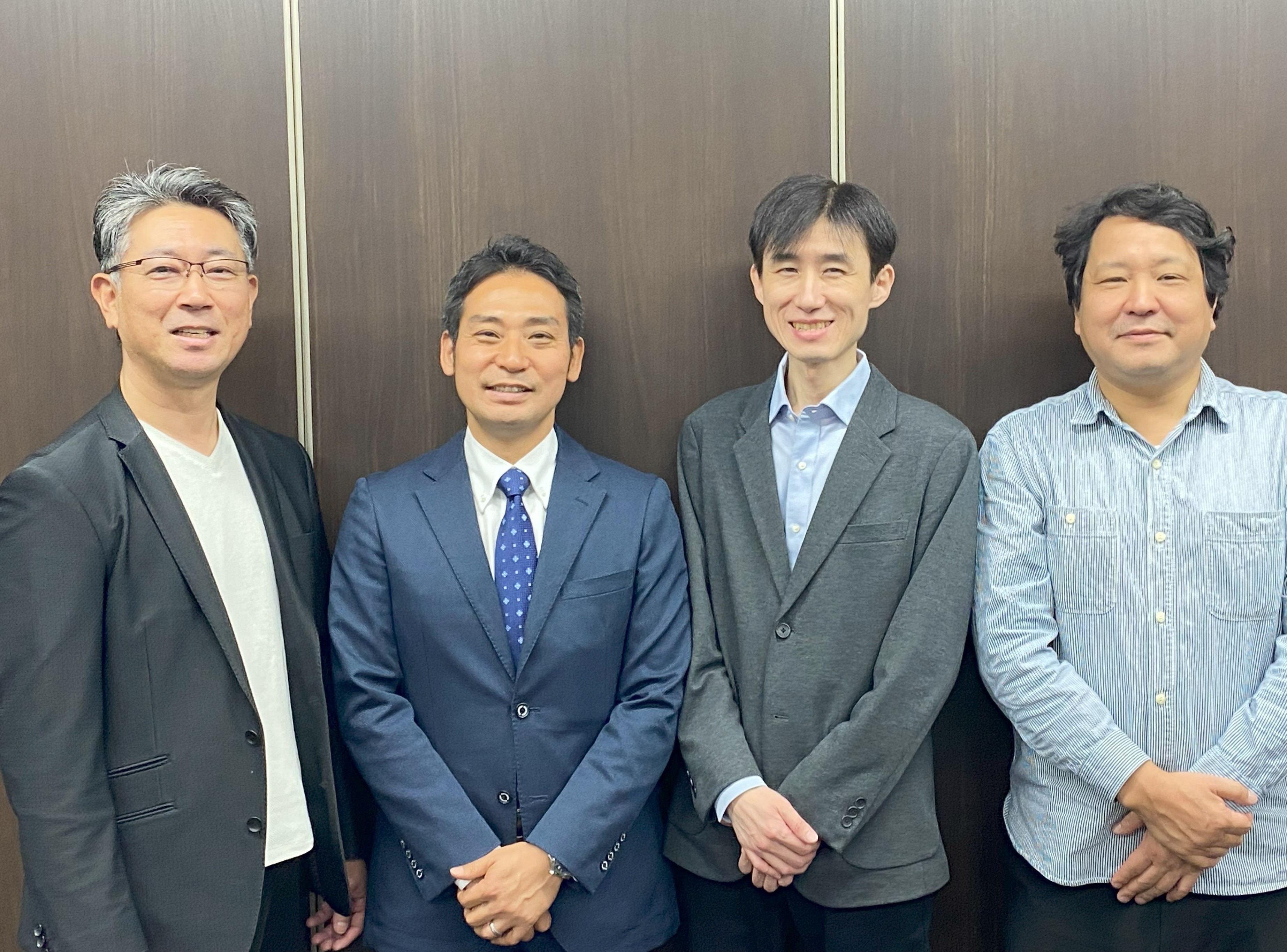
このたびエッセンス株式会社では、「未来を創る人事のリレートーク」を新たにスタートすることになりました。毎回、多彩なゲストをお迎えし、それぞれのご経験や想いを語っていただくとともに、次回のゲストをご紹介いただくリレー形式で進行します。つながりを広げながら、共に豊かな未来を描いていく対話の場として育ててまいります。
(写真左より:エッセンス米田氏、蓜島氏、渡辺氏、高橋氏)
(写真左より:エッセンス米田氏、蓜島氏、渡辺氏、高橋氏)
<ファシリテーター>
蓜島 資幸(はいじま もとゆき)氏 PowerXus株式会社 代表取締役
<ゲスト>
渡辺 剛史(わたなべ つよし)氏 Al inside株式会社 Human Resource Development Division Director
高橋 正明(たかはし まさあき)氏 エッセンス株式会社 取締役兼HCM事業部長
※詳細プロフィールは、Part1の記事をご覧ください。
<特別出演>
米田 瑛紀(よねだ えいき)氏 エッセンス株式会社 代表取締役
プロフィール:2009年にエッセンス株式会社を設立。
プロ人材のシェアリング事業「プロパートナーズ」を立ち上げる。
2017年には大手社員のベンチャー留学「他社留学」、
2018年には大手企業同士による異業種交流型の越境留学「プロボノ」事業を開始。
経済産業省「人材強化研究会」有識者委員も歴任。
2025年には異業種交流型リーダー育成プログラム「ネクストフォーラム」を始動。
高橋さん(以下、高橋) 越境した多くの方が、自分の会社をより好きになるんですよね。
渡辺さん(以下、渡辺) わかります。参加者は皆、研修後に「やっぱりうちの会社っていいな」と言っていました。
高橋 大手企業では分業化されているため、自分の担当範囲は限られていますが、ベンチャー企業に越境すると、担当が一人しかいないことが多く、全ての役割を担わなければならなくなります。そのため、色々なことを一手にこなすことになるのですが、これまでやったことがないことにも対応しなければいけなくなるので、わからないことも多いんですね。そのため、自分の会社に戻って色々な人に質問することになり、いかにリソースが豊富だったかに気づくんです。
蓜島さん(以下、蓜島) そういった経験を通じてリソースの重要性に気づくのは大きな収穫ですよね。ところで、越境研修の参加前に人事の方から「越境先に転職することにならないか?」と心配されることはありませんでしたか?今日はエッセンスの他社留学サービスを立ち上げた米田社長も同席いただいているので、少しお話をお伺いできればと思うのですが、よろしいですか?
米田さん(以下、米田) はい、大丈夫です。転職の心配ですよね、実際ありました。これが当社の他社留学サービスを立ち上げたときの一番のハードルでした。そのため、ご心配される人事の方に対しては、「実際に優秀な人材が離職してしまっている現状があるんですよね。それであれば、敢えて違う環境を体験させる研修を作ってしまった方が人材が定着する可能性が高まるのではないですか?」とお伝えしました。それで実際に導入していただいた企業の多くが効果を実感し、当初のご心配も払拭されました。
蓜島 実際に導入していただくことで、越境の価値をご実感いただけたのですね。
米田 そうです。確かに会社ごとに戦略が色々あって「戦略人事として何をするべきか」という点で、越境がその手段の一つとしてマッチするのかもしれません。ただ、それはそれとして、越境の本質は「井の中の蛙から脱却すること」にあります。環境を変えることで、俯瞰的な視点や客観性を持つことができ、それが新たな価値を生むんです。今後のリーダーには、客観性を持つことが求められています。人的資本経営の観点から見ても、この“自分を客観視する力”は非常に重要だと感じています。
越境経験は、そうした客観性を育むうえで大きな意味を持ちます。リーダーシップやマネジメントにおいても、越境は非常に重要な要素であり、今後さらに広まっていく可能性が高いと考えています。自分を客観視できて初めて得られる発想や刺激、恐怖や喜びといった感情の揺れは、リーダーとしての成長に直結します。だからこそ、客観性を得られるような環境に身を置くことが非常に大切だと思っています。とはいえ、こうした価値を言葉だけで伝えても、人事としての決裁を得るのはなかなかスムーズではないのが現状です。
渡辺さん(以下、渡辺) わかります。参加者は皆、研修後に「やっぱりうちの会社っていいな」と言っていました。
高橋 大手企業では分業化されているため、自分の担当範囲は限られていますが、ベンチャー企業に越境すると、担当が一人しかいないことが多く、全ての役割を担わなければならなくなります。そのため、色々なことを一手にこなすことになるのですが、これまでやったことがないことにも対応しなければいけなくなるので、わからないことも多いんですね。そのため、自分の会社に戻って色々な人に質問することになり、いかにリソースが豊富だったかに気づくんです。
蓜島さん(以下、蓜島) そういった経験を通じてリソースの重要性に気づくのは大きな収穫ですよね。ところで、越境研修の参加前に人事の方から「越境先に転職することにならないか?」と心配されることはありませんでしたか?今日はエッセンスの他社留学サービスを立ち上げた米田社長も同席いただいているので、少しお話をお伺いできればと思うのですが、よろしいですか?
米田さん(以下、米田) はい、大丈夫です。転職の心配ですよね、実際ありました。これが当社の他社留学サービスを立ち上げたときの一番のハードルでした。そのため、ご心配される人事の方に対しては、「実際に優秀な人材が離職してしまっている現状があるんですよね。それであれば、敢えて違う環境を体験させる研修を作ってしまった方が人材が定着する可能性が高まるのではないですか?」とお伝えしました。それで実際に導入していただいた企業の多くが効果を実感し、当初のご心配も払拭されました。
蓜島 実際に導入していただくことで、越境の価値をご実感いただけたのですね。
米田 そうです。確かに会社ごとに戦略が色々あって「戦略人事として何をするべきか」という点で、越境がその手段の一つとしてマッチするのかもしれません。ただ、それはそれとして、越境の本質は「井の中の蛙から脱却すること」にあります。環境を変えることで、俯瞰的な視点や客観性を持つことができ、それが新たな価値を生むんです。今後のリーダーには、客観性を持つことが求められています。人的資本経営の観点から見ても、この“自分を客観視する力”は非常に重要だと感じています。
越境経験は、そうした客観性を育むうえで大きな意味を持ちます。リーダーシップやマネジメントにおいても、越境は非常に重要な要素であり、今後さらに広まっていく可能性が高いと考えています。自分を客観視できて初めて得られる発想や刺激、恐怖や喜びといった感情の揺れは、リーダーとしての成長に直結します。だからこそ、客観性を得られるような環境に身を置くことが非常に大切だと思っています。とはいえ、こうした価値を言葉だけで伝えても、人事としての決裁を得るのはなかなかスムーズではないのが現状です。

(写真:米田氏)
高橋 越境に関わっていて思うのは、自分から「これをやりたい」と思って参加する人よりも、「なんか面白そうだな」と感じて参加した人の方が結果的に良い結果をもたらしているような気がします。越境というのは予定調和じゃないんですよね。予定調和で「こうだろう」と思っていた人は、結果的に成長しにくいと感じています。また、本来的な自立したキャリアを築くためには、「これが自分にとって有益だろう」と自分で判断して手を挙げることが一番大事だと思います。面白くなければ、続けられないし、成長も難しいですよね。「やらされ感」がある人はしんどくなってしまいます。「これは自分にとって足しになる」と思って手を挙げている人は、間違いなくプラスになります。
米田 「井の中の蛙から出る」—これがまさに私たちの研修の原点です。特に大手企業に新卒で入り、そのまま社内だけでキャリアを積んできた多くの人たちは、30代、40代になっても“外”を知らずに過ごしてしまう。そういう現実があるからこそ、「一度外に出て、違う世界を見て、自分や自社を客観的に捉えてみよう」という体験が、ものすごく価値のあるものになる。だからこそ、「井の中の蛙から脱却すること」自体が大事なテーマだと思っています。
各社の中期経営計画や有価証券報告書を見れば、それぞれの人事戦略の方向性はある程度わかります。でも、実際にその計画に紐づいた人事戦略をきちんと組み立てているかと言えば、意識の高い人事もいれば、そうでないケースも確実にありますよね。だからこそ、「客観性を持つことのできる環境」自体が、とても大切なんです。外の視点に触れることで初めてわかることもあるし、実際にやってみないとわからない部分も多いです。でも、究極的には、“外に出たことがないこと自体“がもはや課題なのでは?と思います。
高橋 外に出ることは価値があるのですが、どうしても「〇〇を学ぶ」という具体的な理由がないと、決裁を得るのは難しいんですよね。
蓜島 越境研修を企画検討、提案する際、越境に関する調査結果やアンケート等は確認していらっしゃいますか?
渡辺 見ています。ほぼ100%に近いくらい、ポジティブな結果になっています。越境系に関してネガティブな声はほとんどありません。皆さん、やはり気づきの幅が非常に大きいと感じているようです。客観的に自分を見られるようになって、「自分の会社って良い会社だったんだ」と初めて気づけたという声もあります。人脈も広がりますし、そういった変化は中にいるだけではなかなか得られないんですよね。
蓜島 人材開発とは、ある意味で組織に揺らぎを与えることでもあります。これまでの流れを変えようとすれば、当然、反対意見や抵抗が出るのは自然なことです。また、過去のアンケート結果を上回らなければ成功とは言えない、という暗黙の前提が存在していることもありますよね。
高橋 当社には、経営サイドから直接オーダーが来るケースもあります。例えば、社長が「この会社の古い体制を壊したい。そんなことをやっている時代じゃない」と考えていて、人事に指示をしても動かないから経営企画室長や調査部に調べさせて当社に繋がる、というような流れでお話をいただくケースも多くなっています。
渡辺 それは人事部門に課題があり、人事が期待に応えられていないということですね。
高橋 人事がHRBPの話に慣れていない場合でも、意外と上層部が理解していることが多かったりするのではないかと思います。
米田 「井の中の蛙から出る」—これがまさに私たちの研修の原点です。特に大手企業に新卒で入り、そのまま社内だけでキャリアを積んできた多くの人たちは、30代、40代になっても“外”を知らずに過ごしてしまう。そういう現実があるからこそ、「一度外に出て、違う世界を見て、自分や自社を客観的に捉えてみよう」という体験が、ものすごく価値のあるものになる。だからこそ、「井の中の蛙から脱却すること」自体が大事なテーマだと思っています。
各社の中期経営計画や有価証券報告書を見れば、それぞれの人事戦略の方向性はある程度わかります。でも、実際にその計画に紐づいた人事戦略をきちんと組み立てているかと言えば、意識の高い人事もいれば、そうでないケースも確実にありますよね。だからこそ、「客観性を持つことのできる環境」自体が、とても大切なんです。外の視点に触れることで初めてわかることもあるし、実際にやってみないとわからない部分も多いです。でも、究極的には、“外に出たことがないこと自体“がもはや課題なのでは?と思います。
高橋 外に出ることは価値があるのですが、どうしても「〇〇を学ぶ」という具体的な理由がないと、決裁を得るのは難しいんですよね。
蓜島 越境研修を企画検討、提案する際、越境に関する調査結果やアンケート等は確認していらっしゃいますか?
渡辺 見ています。ほぼ100%に近いくらい、ポジティブな結果になっています。越境系に関してネガティブな声はほとんどありません。皆さん、やはり気づきの幅が非常に大きいと感じているようです。客観的に自分を見られるようになって、「自分の会社って良い会社だったんだ」と初めて気づけたという声もあります。人脈も広がりますし、そういった変化は中にいるだけではなかなか得られないんですよね。
蓜島 人材開発とは、ある意味で組織に揺らぎを与えることでもあります。これまでの流れを変えようとすれば、当然、反対意見や抵抗が出るのは自然なことです。また、過去のアンケート結果を上回らなければ成功とは言えない、という暗黙の前提が存在していることもありますよね。
高橋 当社には、経営サイドから直接オーダーが来るケースもあります。例えば、社長が「この会社の古い体制を壊したい。そんなことをやっている時代じゃない」と考えていて、人事に指示をしても動かないから経営企画室長や調査部に調べさせて当社に繋がる、というような流れでお話をいただくケースも多くなっています。
渡辺 それは人事部門に課題があり、人事が期待に応えられていないということですね。
高橋 人事がHRBPの話に慣れていない場合でも、意外と上層部が理解していることが多かったりするのではないかと思います。
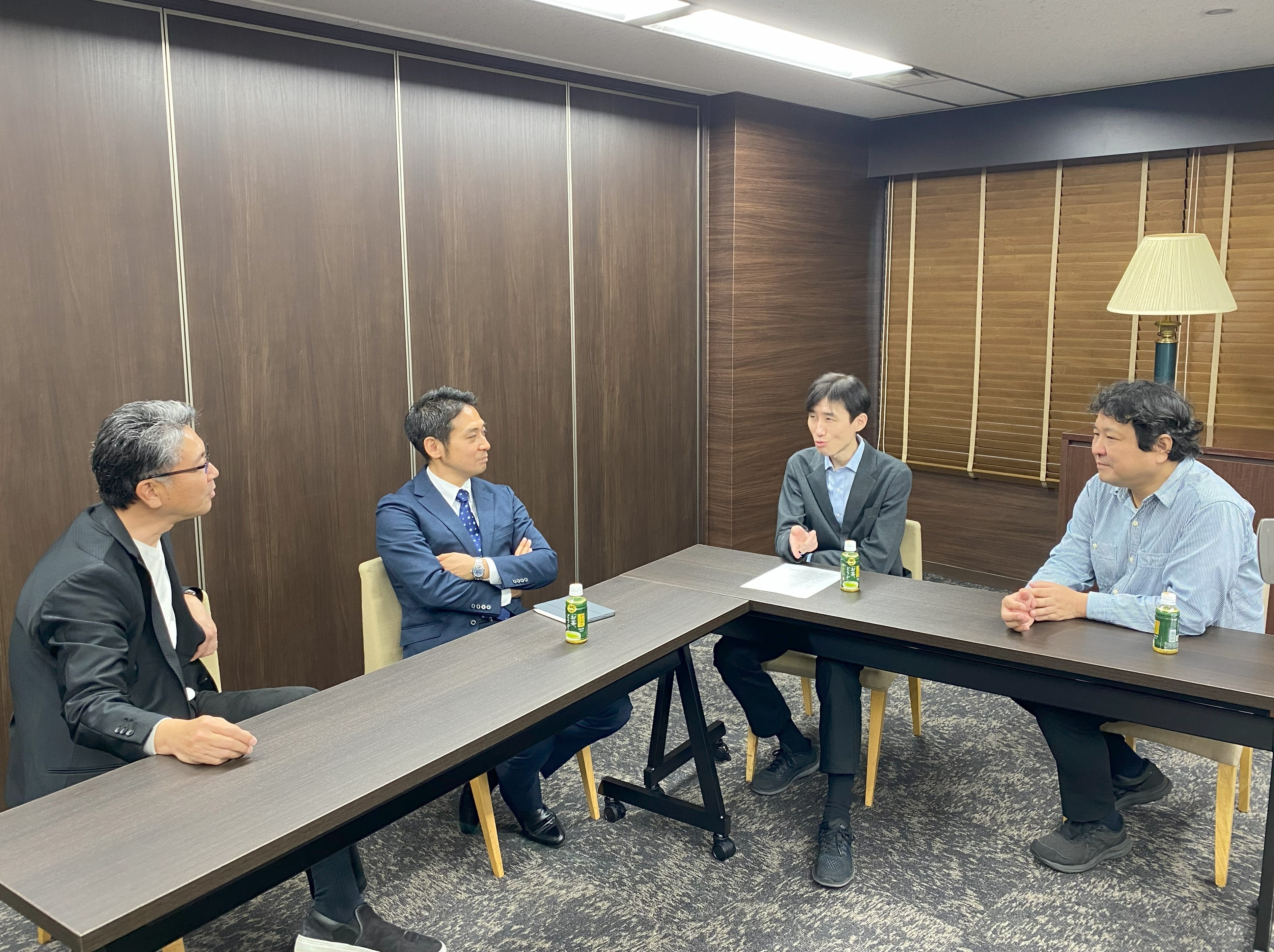
(写真は左から米田氏、蓜島氏、渡辺氏、高橋氏)
蓜島 私の知っている会社で、階層別教育をやめてしまったところがあるんですが、それはジョブ型人事の考え方に沿っているんですよね。つまり、「あるポストを担うには、それに見合う能力が必要。だから、自分で学んで備えなさい」というスタンスです。でも、それって言い方を変えれば、個人への丸投げにも見えて、結構な“無茶ぶり感”があるとも感じています。
高橋 自分もそういう年齢なので実感するのですが、40〜50代の層は、社名で動くことに慣れているんですよね。「自分が何をしたいか」ではなく、「会社から言われたからやる」という動き方、会社の“代表”として振る舞うことには慣れているけれど、自分自身の意思で動くという発想はあまり育っていない。だからこそ、「なぜ学ぶのか」「何のために取り組むのか」を自分事として考える力が必要で、そこが下の世代との大きな違いでもあるんです。でも、おそらくジョブ型が進むと、これまで「社名で動いてきた」人たちにとっては、とても厳しい状況になると思います。一方で、“個”としてキャリアを築いていく人たちは、これからは自ら手を挙げて、自分の意思で道を切り開いていく時代になっていくんでしょうね。
蓜島 自分でも学習する人が増えていくと思いますが、結果的にそこで得られるものはグローバルスタンダード、つまり普遍的なスタンダードに過ぎないんですよね。でも、それだけでは十分ではなく、会社や管理職が大切にしているアイデンティティやオリジン、つまり企業の根底にある価値観や文化は、しっかり学ぶ必要があります。そこは捨ててしまってはいけないんです。自己学習だけでは足りないんです。
高橋 越境プログラムを検討されているお客様からよく質問されるのが、「グループ内の出向と何が違うのか」という点です。グループ内の出向では、基本的に同質性を学ぶことになります。グループ内の会社に出向すれば、同じフィロソフィーに則っているので、それを学ぶならいいのですが、今の課題はその同質性が問題になっているという点です。多様化を進めるためには、グループ内出向では限界があります。だからこそ、単に「どちらか一方」というわけではなく、両方をうまく取り入れ、バランスをとらないといけないと思います。
蓜島 出向先のマネージャーは、基本的に上から降りてきている人が多いですよね。出向先のマネージャーが同じような考え方を持っている場合、変革や多様な視点を得ることが難しくなります。血が違うところに行かなければならないと思います。
高橋 そうじゃないと気づきが少ないと思いますし、自分の会社を真剣に、深く見つめるためには、外の視点が欠かせないと感じます。
渡辺 それは本当に思います。外に出ることで、まるで“幽体離脱”したかのように、客観的に自分の会社や組織を見ることができるんですよね。
米田 自社を外部の視点で見ること自体が、非常に価値のあることだと思います。自社を客観的に捉えることは、まさに「井の中の蛙」に気づくきっかけになります。こうした気づきがあると、実はたくさんの課題やテーマが見えてくるんです。しかし、個別の企業で行う研修では、こうした視点を得る機会が少ないことが多いんですよね。だからこそ、自社を客観的に見るためのプロジェクトを作り、その過程でどのように気づき、それを実践に繋げていくかが重要だと思います。
高橋 自分もそういう年齢なので実感するのですが、40〜50代の層は、社名で動くことに慣れているんですよね。「自分が何をしたいか」ではなく、「会社から言われたからやる」という動き方、会社の“代表”として振る舞うことには慣れているけれど、自分自身の意思で動くという発想はあまり育っていない。だからこそ、「なぜ学ぶのか」「何のために取り組むのか」を自分事として考える力が必要で、そこが下の世代との大きな違いでもあるんです。でも、おそらくジョブ型が進むと、これまで「社名で動いてきた」人たちにとっては、とても厳しい状況になると思います。一方で、“個”としてキャリアを築いていく人たちは、これからは自ら手を挙げて、自分の意思で道を切り開いていく時代になっていくんでしょうね。
蓜島 自分でも学習する人が増えていくと思いますが、結果的にそこで得られるものはグローバルスタンダード、つまり普遍的なスタンダードに過ぎないんですよね。でも、それだけでは十分ではなく、会社や管理職が大切にしているアイデンティティやオリジン、つまり企業の根底にある価値観や文化は、しっかり学ぶ必要があります。そこは捨ててしまってはいけないんです。自己学習だけでは足りないんです。
高橋 越境プログラムを検討されているお客様からよく質問されるのが、「グループ内の出向と何が違うのか」という点です。グループ内の出向では、基本的に同質性を学ぶことになります。グループ内の会社に出向すれば、同じフィロソフィーに則っているので、それを学ぶならいいのですが、今の課題はその同質性が問題になっているという点です。多様化を進めるためには、グループ内出向では限界があります。だからこそ、単に「どちらか一方」というわけではなく、両方をうまく取り入れ、バランスをとらないといけないと思います。
蓜島 出向先のマネージャーは、基本的に上から降りてきている人が多いですよね。出向先のマネージャーが同じような考え方を持っている場合、変革や多様な視点を得ることが難しくなります。血が違うところに行かなければならないと思います。
高橋 そうじゃないと気づきが少ないと思いますし、自分の会社を真剣に、深く見つめるためには、外の視点が欠かせないと感じます。
渡辺 それは本当に思います。外に出ることで、まるで“幽体離脱”したかのように、客観的に自分の会社や組織を見ることができるんですよね。
米田 自社を外部の視点で見ること自体が、非常に価値のあることだと思います。自社を客観的に捉えることは、まさに「井の中の蛙」に気づくきっかけになります。こうした気づきがあると、実はたくさんの課題やテーマが見えてくるんです。しかし、個別の企業で行う研修では、こうした視点を得る機会が少ないことが多いんですよね。だからこそ、自社を客観的に見るためのプロジェクトを作り、その過程でどのように気づき、それを実践に繋げていくかが重要だと思います。

(写真は左から米田氏、蓜島氏)
渡辺 まさにその通りです。「地球は青かった」という言葉のように、外の世界に出ることで、それまで自分が見ていたものがいかに限られていたかに気づく瞬間は、非常に大きな意味を持ちます。
米田 越境は確かに手段です。しかし、その手段が今まで当たり前だと思っていたことを変革する大きな手段になると考えています。そうした変革の手段として越境研修を提供していきたいですね。
米田 越境は確かに手段です。しかし、その手段が今まで当たり前だと思っていたことを変革する大きな手段になると考えています。そうした変革の手段として越境研修を提供していきたいですね。
蓜島 今日の冒頭で「人材開発はあまり変わっていないのではないか」という話がありましたが、最近は大きなテーマとして“人的資本”が注目されています。これまで「リソース」とされていた人材が「資本」として捉えられるようになり、そこに投資が必要だという考え方に変わってきています。そうなると、人材育成の中でも、人的資本という視点を意識することが重要になりますし、越境的な取り組みなどを戦略と結びつけて、その価値をどう捉えるかも考えていく必要があると思うのですが。
渡辺 「人的資本経営」という言葉が注目されるようになって、まだ数年しか経っていませんが、やはり“人的資本”と言うからには、人を資本、つまり投資の対象と捉える必要があります。そして、投資するということは、当然そこにリターンを期待しているわけです。今はまず「人的資本を可視化すること」が最初のステップとしてあって、多くの企業が数値化や定量的な見える化から始めています。でも本来は、きちんと人に投資をして、その結果としてリターンが生まれ、それを企業が享受して成長していく—そんなサイクルが理想だと思います。
一方で、個人にはそれぞれ生活や人生があるわけで、企業と個人が対等なバランスの中で、双方が幸せになることが大切だと思います。その中で「越境」は一つの手段だと思いますが、現時点ではまだ“投資に対するリターン”が見えにくく、効果の測定もしづらいというのが正直なところです。手段としては有効だと思いますが、まだ曖昧でふわっとした印象を持たれている面もあります。私自身も人事ですが、こういった取り組みを会社で決裁を通すとなると、やはりハードルは高いと感じます。
とはいえ、そこから得られる期待値や可能性も確実にあると思います。実際、さまざまな企業がすでに越境の取り組みを始めていますし、エッセンスの提供しているような越境研修に参加して、そこで得た定性的な気づきや学び、場合によっては定量的な成果も、少しずつ見え始めてきていると感じます。そうした事例を丁寧にキャッチしていくことで、「自社でもこうした価値を得られるのでは」と思えるようになりますし、それが“リターン”として見えてくるのだと思います。今はまだトライアル段階の企業も多いですが、少しずつ広がってきている印象があります。
もちろん、定性的・定量的にリターンを示すのは難しいかもしれませんが、たとえ定性的なものであっても、リターンとして期待できるのであれば、それを材料にして会社の決裁を通していく、というアプローチはあると思います。ハードルはありますが、可能性は十分あると思います。私自身も、以前は勢いで進めたこともありましたが、やはり大事なのは「目的」です。人的資本の観点もありますが、最終的には“事業を強くする”ということや、自社の中で人事に今求められている機能や役割をしっかり見据えることが大切だと思います。
改めて見直してみると、やはり人事の取り組みを強化することで、会社の事業や企業の継続性に繋げていけると思います。それをしっかり構築できれば、おそらく成功するのではないでしょうか。ただ、それを実現するのは簡単ではなく、悩んでいる企業が多いと思います。そういった企業が、さまざまな方々と議論できる場があると、共通の解決策を見つけられるかもしれません。各社それぞれ事情はありますが、共通の目的を見つけ、面白いことができるようになれば、企業の成長や発展につながります。人的資本に対する投資とその後のリターンをしっかり作ることができるようになり、人事の役割もより明確に求められるようになると思います。実際、あきらめている人事の方も多いかもしれませんが、「頑張りましょう」と言いたいです。
蓜島 リターンとして、「エンゲージメント」や「離職率」といった中間指標を使って判断しているように思うのですが、本来であれば、全体の業績や成果に繋がっていなければいけないですよね。でも、まだそれが不確定なので、定性的なものであっても構わないのではないかと感じます。
渡辺 「人的資本経営」という言葉が注目されるようになって、まだ数年しか経っていませんが、やはり“人的資本”と言うからには、人を資本、つまり投資の対象と捉える必要があります。そして、投資するということは、当然そこにリターンを期待しているわけです。今はまず「人的資本を可視化すること」が最初のステップとしてあって、多くの企業が数値化や定量的な見える化から始めています。でも本来は、きちんと人に投資をして、その結果としてリターンが生まれ、それを企業が享受して成長していく—そんなサイクルが理想だと思います。
一方で、個人にはそれぞれ生活や人生があるわけで、企業と個人が対等なバランスの中で、双方が幸せになることが大切だと思います。その中で「越境」は一つの手段だと思いますが、現時点ではまだ“投資に対するリターン”が見えにくく、効果の測定もしづらいというのが正直なところです。手段としては有効だと思いますが、まだ曖昧でふわっとした印象を持たれている面もあります。私自身も人事ですが、こういった取り組みを会社で決裁を通すとなると、やはりハードルは高いと感じます。
とはいえ、そこから得られる期待値や可能性も確実にあると思います。実際、さまざまな企業がすでに越境の取り組みを始めていますし、エッセンスの提供しているような越境研修に参加して、そこで得た定性的な気づきや学び、場合によっては定量的な成果も、少しずつ見え始めてきていると感じます。そうした事例を丁寧にキャッチしていくことで、「自社でもこうした価値を得られるのでは」と思えるようになりますし、それが“リターン”として見えてくるのだと思います。今はまだトライアル段階の企業も多いですが、少しずつ広がってきている印象があります。
もちろん、定性的・定量的にリターンを示すのは難しいかもしれませんが、たとえ定性的なものであっても、リターンとして期待できるのであれば、それを材料にして会社の決裁を通していく、というアプローチはあると思います。ハードルはありますが、可能性は十分あると思います。私自身も、以前は勢いで進めたこともありましたが、やはり大事なのは「目的」です。人的資本の観点もありますが、最終的には“事業を強くする”ということや、自社の中で人事に今求められている機能や役割をしっかり見据えることが大切だと思います。
改めて見直してみると、やはり人事の取り組みを強化することで、会社の事業や企業の継続性に繋げていけると思います。それをしっかり構築できれば、おそらく成功するのではないでしょうか。ただ、それを実現するのは簡単ではなく、悩んでいる企業が多いと思います。そういった企業が、さまざまな方々と議論できる場があると、共通の解決策を見つけられるかもしれません。各社それぞれ事情はありますが、共通の目的を見つけ、面白いことができるようになれば、企業の成長や発展につながります。人的資本に対する投資とその後のリターンをしっかり作ることができるようになり、人事の役割もより明確に求められるようになると思います。実際、あきらめている人事の方も多いかもしれませんが、「頑張りましょう」と言いたいです。
蓜島 リターンとして、「エンゲージメント」や「離職率」といった中間指標を使って判断しているように思うのですが、本来であれば、全体の業績や成果に繋がっていなければいけないですよね。でも、まだそれが不確定なので、定性的なものであっても構わないのではないかと感じます。

(写真は左から渡辺氏、高橋氏)
渡辺 急に「会社の業績につながりました」と証明するのは難しいと思います。中間指標やエンゲージメント、離職率など、まずはそういったデータを収集することが第一歩だと思います。これらのデータを取って、開示する段階に来ていると思います。その先に、会社の業績や生産性、一人当たりの何かしらの指標に繋がるメカニズムが見えてくるのではないかと思います。もっと研究や学術的な進展があれば、関係性が明確にわかるようになると思います。まだそこは解明されていない部分が多いですが、進んでいけば、間接的に業績につながり、じわじわと貢献できるようになっているということが証明されるのではないかと思います。
蓜島 単純に「やったことが結果に繋がった」という形ではなく、例えば研修を実施した結果「一人あたりいくら増えた」という具体的な数字で測るのではなく、戦略的に新しいことに挑戦し、その過程で得られた定性的な評価や成果を集めていくということですかね?
渡辺 そうだと思います。定量的に測るのは難しいと思います。これはフェーズの問題かもしれませんし、時代が進むことで徐々に解明されていく部分もあるかもしれません。そこに対しては期待しています。
蓜島 単純に「やったことが結果に繋がった」という形ではなく、例えば研修を実施した結果「一人あたりいくら増えた」という具体的な数字で測るのではなく、戦略的に新しいことに挑戦し、その過程で得られた定性的な評価や成果を集めていくということですかね?
渡辺 そうだと思います。定量的に測るのは難しいと思います。これはフェーズの問題かもしれませんし、時代が進むことで徐々に解明されていく部分もあるかもしれません。そこに対しては期待しています。
共に悩み挑戦する人事コミュニティの必要性
蓜島 こういったことをみんなで悩みながら、人事としてムーブメントを起こしていこうという期待を込めて、渡辺さんと一緒にこうした会話をしていける仲間を集めていけるといいですよね。同じ想いを持つ皆様に対してメッセージを頂戴できますか?
渡辺 「皆さん、一緒に悩みませんか?」とお伝えしたいです。一人で、一社で人事の仕事をしていて、会社内で悩んでいるだけでは限界があると思います。これもダイバーシティの一環かもしれませんが、様々な会社の人事が集まって話をしていれば、新たな気づきが得られると思うんです。日本にはこういったコミュニティが少ない気がしていて、フラットな環境で、色々な企業の人事が集まる場があってもいいと思います。それが実現できれば、きっと有意義なコミュニティになるのではないかと思います。
蓜島 人事が保守的にならず、失敗を恐れず、みんなで考えてチャレンジしていける環境を作ることが大切ですよね。まずはスモールスタートを切ることができたらいいですね。
渡辺 まずは小さな成功体験やトライアルを実施して、たとえエラーがあっても、何もしないよりは確実に前進します。エラーから学ぶことも多いですし、それだけでも前に進んだと言えると思います。それだけでも一緒にやりたいですね。もしくは、他の会社のエラーを共有することだけでも、他の企業にとってはプラスになります。情報交換をしながら、共に成長できる場があれば良いなと思います。
蓜島 入り口の手段として、まずは一緒にその可能性を考えてみることから始められたらいいですね。渡辺さんと一緒に考えてみたい人事の皆さん、是非エッセンスに問い合わせてください!(笑) 本日は皆さん、ありがとうございました。
渡辺 「皆さん、一緒に悩みませんか?」とお伝えしたいです。一人で、一社で人事の仕事をしていて、会社内で悩んでいるだけでは限界があると思います。これもダイバーシティの一環かもしれませんが、様々な会社の人事が集まって話をしていれば、新たな気づきが得られると思うんです。日本にはこういったコミュニティが少ない気がしていて、フラットな環境で、色々な企業の人事が集まる場があってもいいと思います。それが実現できれば、きっと有意義なコミュニティになるのではないかと思います。
蓜島 人事が保守的にならず、失敗を恐れず、みんなで考えてチャレンジしていける環境を作ることが大切ですよね。まずはスモールスタートを切ることができたらいいですね。
渡辺 まずは小さな成功体験やトライアルを実施して、たとえエラーがあっても、何もしないよりは確実に前進します。エラーから学ぶことも多いですし、それだけでも前に進んだと言えると思います。それだけでも一緒にやりたいですね。もしくは、他の会社のエラーを共有することだけでも、他の企業にとってはプラスになります。情報交換をしながら、共に成長できる場があれば良いなと思います。
蓜島 入り口の手段として、まずは一緒にその可能性を考えてみることから始められたらいいですね。渡辺さんと一緒に考えてみたい人事の皆さん、是非エッセンスに問い合わせてください!(笑) 本日は皆さん、ありがとうございました。
