【未来を創る人事のリレートーク】人材開発と越境研修
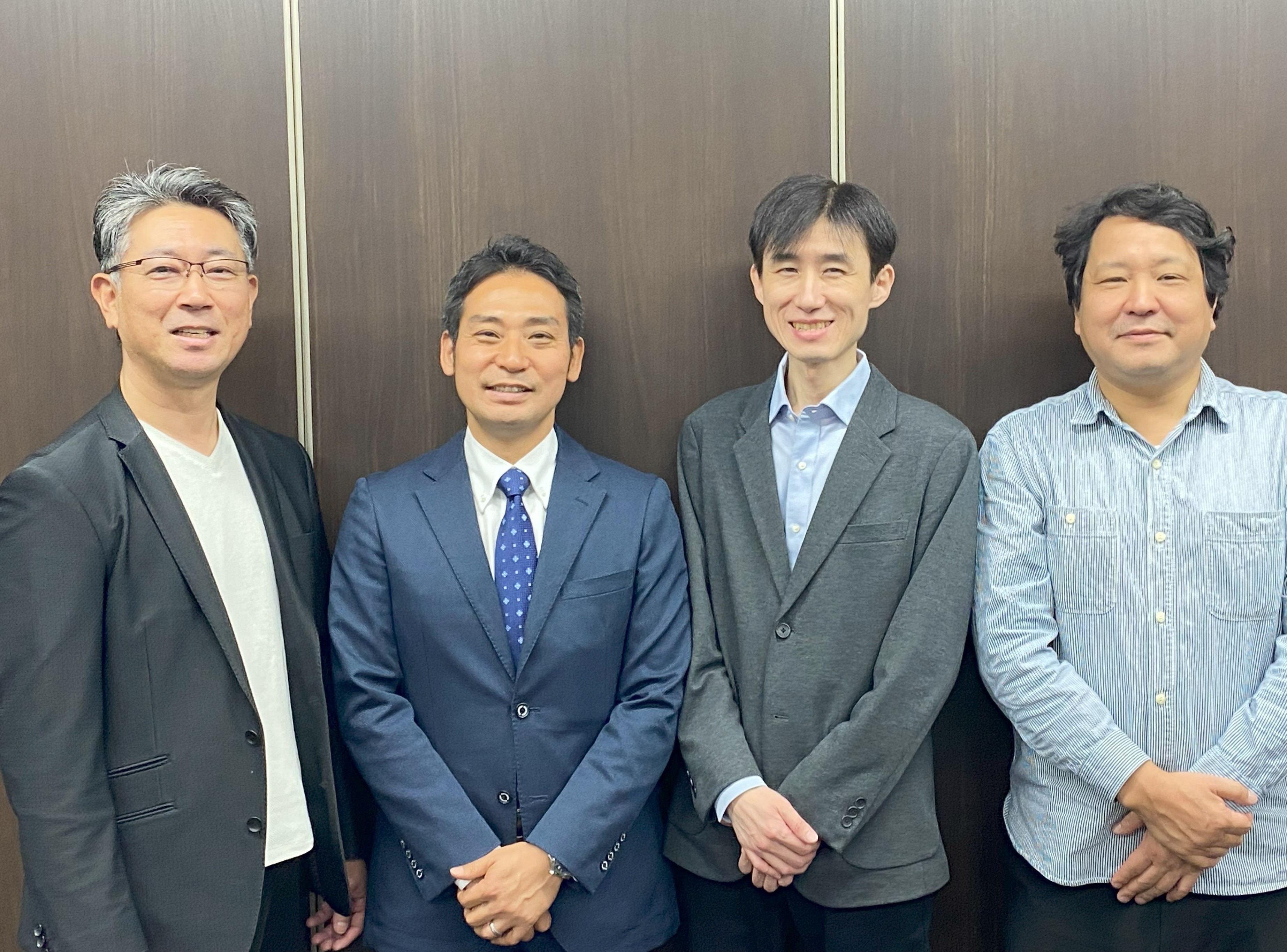
このたびエッセンス株式会社では、「未来を創る人事のリレートーク」を新たにスタートすることになりました。毎回、多彩なゲストをお迎えし、それぞれのご経験や想いを語っていただくとともに、次回のゲストをご紹介いただくリレー形式で進行します。つながりを広げながら、共に豊かな未来を描いていく対話の場として育ててまいります。
(写真左より:エッセンス米田氏、蓜島氏、渡辺氏、高橋氏)
(写真左より:エッセンス米田氏、蓜島氏、渡辺氏、高橋氏)
Part2:これからの人材育成のあり方とは
Part1の記事では、人材開発の現状や越境研修の魅力についての話が中心でした(記事はこちら)。今回は引き続きファシリテーターの蓜島さんの進行で、事業戦略と連動した人材開発、会社の枠を越えた人材育成について、手段ではなく目的を重視することの重要性などについて、渡辺さんは人事の立場から、高橋さんは研修を提供する企業の立場からお話いただきました。
<ファシリテーター>
蓜島 資幸(はいじま もとゆき)氏 PowerXus株式会社 代表取締役
<ゲスト>
・渡辺 剛史(わたなべ つよし)氏
Al inside株式会社 Human Resource Development Division Director
・高橋 正明(たかはし まさあき)氏 エッセンス株式会社 取締役兼HCM事業部長
※詳細プロフィールは、Part1の記事をご覧ください。
蓜島さん(以下、蓜島) 越境研修は比較的新しい取り組みなので、導入に際して社内の承認を得るのにご苦労されましたか?
渡辺さん(以下、渡辺) はい、苦労しました。正直なところ、勢いも必要だと感じています。詳細を説明した際、すぐに理解してもらうのは難しいと感じたため、「時代として必要だ」という理由を前面に出し、勢いに任せて進めた部分もあります。
蓜島 起案するにあたって、経営陣に響いたキーワードはありますか?
渡辺 事業戦略側との連携が大きなポイントだと思います。人事が「やりたいからやる」ということではなく、根本的には、新規事業を立ち上げないと会社が今後のビジョンに向かって進めないという大きな目的があります。そのため、新規事業の立ち上げは重要なピースとなり、その実現のために何をすべきか、組織として、人材としてどう整えていくかが問われます。事業部門は既存の事業が進行中である一方で、新規事業は急には進められないという現実もあります。だからこそ、その入り口、スタートとして人材開発を通じて、まずはマインドを醸成していくことが必要で、その手段として越境研修が有効だと考え、そこに繋げました。
つまり、人事が勝手に進めるのではなく、事業戦略側と連携して新規事業としっかり繋がった設計をしました。さきほど「勢いで」と申し上げましたが、その部分は事業戦略側と共に作り上げ、経営陣に説明して同意を得るというプロセスがありました。ただ、難しいのは、効果測定の部分だと思います。
蓜島 事業戦略と人事施策を絡めるという発想をする人事は少ないのではないでしょうか?
渡辺 これは蓜島さんだけではなく、色々な研修ベンダーの方にもよく言われます。渡辺さんみたいな人が人事戦略の責任者をやっていて、事業戦略側の責任者と密にコミュニケーションを取って、それでちゃんと戦略に落として実行に移している企業はなかなかないと言われます。
蓜島 その感性はどこで養ったのですか?
渡辺さん(以下、渡辺) はい、苦労しました。正直なところ、勢いも必要だと感じています。詳細を説明した際、すぐに理解してもらうのは難しいと感じたため、「時代として必要だ」という理由を前面に出し、勢いに任せて進めた部分もあります。
蓜島 起案するにあたって、経営陣に響いたキーワードはありますか?
渡辺 事業戦略側との連携が大きなポイントだと思います。人事が「やりたいからやる」ということではなく、根本的には、新規事業を立ち上げないと会社が今後のビジョンに向かって進めないという大きな目的があります。そのため、新規事業の立ち上げは重要なピースとなり、その実現のために何をすべきか、組織として、人材としてどう整えていくかが問われます。事業部門は既存の事業が進行中である一方で、新規事業は急には進められないという現実もあります。だからこそ、その入り口、スタートとして人材開発を通じて、まずはマインドを醸成していくことが必要で、その手段として越境研修が有効だと考え、そこに繋げました。
つまり、人事が勝手に進めるのではなく、事業戦略側と連携して新規事業としっかり繋がった設計をしました。さきほど「勢いで」と申し上げましたが、その部分は事業戦略側と共に作り上げ、経営陣に説明して同意を得るというプロセスがありました。ただ、難しいのは、効果測定の部分だと思います。
蓜島 事業戦略と人事施策を絡めるという発想をする人事は少ないのではないでしょうか?
渡辺 これは蓜島さんだけではなく、色々な研修ベンダーの方にもよく言われます。渡辺さんみたいな人が人事戦略の責任者をやっていて、事業戦略側の責任者と密にコミュニケーションを取って、それでちゃんと戦略に落として実行に移している企業はなかなかないと言われます。
蓜島 その感性はどこで養ったのですか?

(写真:渡辺氏)
渡辺 それは何でしょうね。自分のキャリアの後半に感じたことなのですが、人事の世界で著名な方々がいらっしゃいますよね。そういった方々のセミナーに参加したり、直接お話ししたりする中で強く感じたのは、「人事の仕事は、会社を強くすることや、社員が幸せになることのためにある」ということなんです。それ以上でもそれ以下でもなく、結局のところ、その目的のために人事があるんだと思っています。だからこそ、会社の中で人事として働いている以上、会社に貢献するという命題は当然のこととしてあると感じています。組織を強くし、会社を強くして、業績を上げていく―それ自体が人材育成の目的であり、ある意味では投資でもあると考えています。そうであるならば、単に個人が「よかった」と感じるだけで終わるのではなく、やはり何らかの形で会社や組織、事業に対するリターンが求められるのは当然だと思います。
ですから、人事が独自に何かを進めるのではなく、「事業とどう結びつけるか」を常に考えていました。ちょうど都築電気に在籍していた当時、事業戦略部門が立ち上がったタイミングでもあったので、当然そことも連携し、責任者とも密にミーティングを重ねながら、「越境プログラムのような仕掛けがないと新規事業は難しいよね」という共通認識のもと、そうした取り組みをセットで提案するようにしていました。募集をかける際にも、「このプログラムは何のためにあるのか」「どんな狙いがあるのか」といった背景や意図をきちんと説明し、企業として何を期待しているのかという命題を伝えるようにしていました。単に個人の幸せのためだけではなく、事業や組織の目的とつながっているという点は、常に意識していた部分です。
ですから、人事が独自に何かを進めるのではなく、「事業とどう結びつけるか」を常に考えていました。ちょうど都築電気に在籍していた当時、事業戦略部門が立ち上がったタイミングでもあったので、当然そことも連携し、責任者とも密にミーティングを重ねながら、「越境プログラムのような仕掛けがないと新規事業は難しいよね」という共通認識のもと、そうした取り組みをセットで提案するようにしていました。募集をかける際にも、「このプログラムは何のためにあるのか」「どんな狙いがあるのか」といった背景や意図をきちんと説明し、企業として何を期待しているのかという命題を伝えるようにしていました。単に個人の幸せのためだけではなく、事業や組織の目的とつながっているという点は、常に意識していた部分です。
蓜島 渡辺さんは現職で3社目となりましたが、当然のことながら、会社ごとに既存の人事制度や仕組みがありますよね。渡辺さんが人事責任者として新しいものをどんどん導入していくと、人事の担当者が十分にいるわけではないため、一人ひとりの仕事が増えていくことになりますよね。そのあたりの割り切り、取捨選択はどうしていたのでしょうか?
渡辺 必要性に応じて優先順位をつけて取り組んでいました。やめたものもありました。「これはやめよう」「これはストップしよう」「お休みしよう」といった形で、バランスを考えていました。全てを増やすだけでは、当然デリバリーがどんどん膨らんでしまい、それではうまくいかないですよね。
蓜島 過去脈々とやってきたものを辞めるには、勇気がいりますよね。
渡辺 全体感や目指している方向性、ビジョンと照らし合わせて、「これは優先順位を少し下げてもいいのでは?」と思った場合は、思い切って止める、やめるという判断をすることがありました。蓜島さんと始めたものについても、時にはストップしたり、お休みしたりすることがありましたよね。それも結局、取捨選択や優先順位付けの一環です。予算も時間も限られていますから。
蓜島 選抜研修など、最初は効果があったとしても、回を重ねるごとに形式的な研修になってしまい、途中でやめればいいのに続けられている、といったことはよくありますよね?
渡辺 私の場合ですが、3回実施して十分「山が崩れたな」と思ったら止めていました。例えば、都築電気で行っていた次世代経営人材育成プログラムも、最初の3年ほど実施した後、ある程度結果が出てきて、山が崩れたと感じた時点で一旦お休みしました。その後、山が再び盛り上がってきたら、もう一度実施するというサイクルを繰り返していました。
蓜島 「山が崩れてきたな」というのは、対象となるターゲットの意識やマインドがかなり変わってきたという判断だったのでしょうか?
渡辺 そうですね、対象となる層には限りがあったため、例えば等級別に対象者を絞って、全員に参加してもらった結果、一定の層に均等に行き渡ったと判断できたら、そこで一度中断しました。そして、再度対象層の母集団が増えてきたタイミングで、もう一度始めるというやり方をしていました。何も考えずに思考停止状態で、ただ繰り返すだけでは意味がないと思うので、毎年度ゼロベースで見直しを行い、継続するべきか、あるいはお休みするべきかを考えていました。
渡辺 必要性に応じて優先順位をつけて取り組んでいました。やめたものもありました。「これはやめよう」「これはストップしよう」「お休みしよう」といった形で、バランスを考えていました。全てを増やすだけでは、当然デリバリーがどんどん膨らんでしまい、それではうまくいかないですよね。
蓜島 過去脈々とやってきたものを辞めるには、勇気がいりますよね。
渡辺 全体感や目指している方向性、ビジョンと照らし合わせて、「これは優先順位を少し下げてもいいのでは?」と思った場合は、思い切って止める、やめるという判断をすることがありました。蓜島さんと始めたものについても、時にはストップしたり、お休みしたりすることがありましたよね。それも結局、取捨選択や優先順位付けの一環です。予算も時間も限られていますから。
蓜島 選抜研修など、最初は効果があったとしても、回を重ねるごとに形式的な研修になってしまい、途中でやめればいいのに続けられている、といったことはよくありますよね?
渡辺 私の場合ですが、3回実施して十分「山が崩れたな」と思ったら止めていました。例えば、都築電気で行っていた次世代経営人材育成プログラムも、最初の3年ほど実施した後、ある程度結果が出てきて、山が崩れたと感じた時点で一旦お休みしました。その後、山が再び盛り上がってきたら、もう一度実施するというサイクルを繰り返していました。
蓜島 「山が崩れてきたな」というのは、対象となるターゲットの意識やマインドがかなり変わってきたという判断だったのでしょうか?
渡辺 そうですね、対象となる層には限りがあったため、例えば等級別に対象者を絞って、全員に参加してもらった結果、一定の層に均等に行き渡ったと判断できたら、そこで一度中断しました。そして、再度対象層の母集団が増えてきたタイミングで、もう一度始めるというやり方をしていました。何も考えずに思考停止状態で、ただ繰り返すだけでは意味がないと思うので、毎年度ゼロベースで見直しを行い、継続するべきか、あるいはお休みするべきかを考えていました。
蓜島 今後、どの企業も新規事業を立ち上げなければ成長が難しいと思いますが、「越境研修」をどのように活用し、どのような目的で取り入れていくのがいいのでしょうか?
渡辺 越境というのは、やはり“手段”にすぎないと思っています。だからこそ、「何のために越境するのか」という視点が大事だと感じています。都築電気で越境プログラムを企画検討した時は、ちょうどトレンドにもなっているし、手を挙げる人もけっこういるんじゃないか、という期待がありました。自分の経験をも基に、「ちょっとやってみようか」と試しに始めてみた部分もあります。最初はトライアルのような感覚でしたが、実際に始めてみると反応が良くて、これはきっと、目的と皆さんの期待がうまくかみ合った結果なのだろうと感じています。
渡辺 越境というのは、やはり“手段”にすぎないと思っています。だからこそ、「何のために越境するのか」という視点が大事だと感じています。都築電気で越境プログラムを企画検討した時は、ちょうどトレンドにもなっているし、手を挙げる人もけっこういるんじゃないか、という期待がありました。自分の経験をも基に、「ちょっとやってみようか」と試しに始めてみた部分もあります。最初はトライアルのような感覚でしたが、実際に始めてみると反応が良くて、これはきっと、目的と皆さんの期待がうまくかみ合った結果なのだろうと感じています。

(写真は左から蓜島氏、渡辺氏、高橋氏)
蓜島 我々が研修などでよく言われるのは、一社単体でビジネスを展開するのではなく、競合企業やパートナーと共創して新しいビジネスを生み出すということです。その際、バックキャストで考える必要があるとされています。しかし、他社と共創する方法がわからず、そもそもネットワークもないため、「時すでに遅し」という状況の企業も多いですよね。
渡辺 そうですね、他社との交流が盛んな会社と、そうでない閉鎖的な会社があって、成長のスピードに差が出てくるのではないかと思います。
蓜島 渡辺さんは、ご自身が参加された越境プログラムに参加した時のネットワークは続いていますか?
渡辺 一部続いています。全員ではありませんが、転職後もそのつながりがきっかけで、ヒアリングに伺ったこともあります。
蓜島 もう何十年も経っていますよね?
渡辺 当時お世話になった方で、お酒をご一緒したこともある方に、ちょっとヒアリングしてみたいと思ったことがありました。名刺をひっくり返してなんとか連絡先をたどり、繋いでもらって、ヒアリングに伺いました。
蓜島 同志のような、仲間がいる感じですかね。
渡辺 そうですね。私が参加者側だった時は、人事になる前で、開発やマーケティング、企画を担当していました。しかし、人事に移ってからは、久しぶりに人事部門にいた方とコンタクトを取ってヒアリングできたので、その点は良かったですね。
蓜島 ネットワーキングを進める際、実際にそれを企画する過程での難しさや、想定される障壁にはどのようなものが考えられるでしょうか?
渡辺 それは会社によると思いますが、企画を始める前の、社内の決裁を通すのがハードルが高いのではないでしょうか。当然、「何のためにやるのか」という目的が大前提だと思います。それがしっかりと説明できるかどうかが大きなポイントです。手段から入ると難しいと思います。確かに越境というやり方は、方法や手段の一つではありますが、それはあくまでツールや方法論に過ぎません。ここから入ってしまうと、どうやってやるか(How)思考になってしまうので、まずは「何のためにやるのか」が先にあるべきです。
そして、越境がちょうどよくオプションとして繋がるように構成できれば理想的ですが、会社によっては、人事の方々がそこまで話を持っていくのが難しい場合もあるようです。そのような文化や慣習があることも考慮しなければならないでしょうし、さまざまな事情もあると思います。そうした点は、ハードルになるかもしれませんね。
蓜島 何社かが集まると、それぞれの会社には異なる目的がありますよね。そのため、1つの目的で1つのイベントを開催するのは難しいですよね。
渡辺 ですので、やはりそういった場を作って、色々な企業がどんな悩みを抱えているのか、特に人事の方々がどんな困りごとを持っているのかを出し合い、議論するのは非常に有意義で興味深いと思います。企業ごとに悩み事は異なり、それこそ多様性だと思うんです。人事の困りごとは様々だと思います。だから、一つのプログラムにみんなで参加するというよりは、それぞれの企業に固有の事情があるので、そういった点も踏まえたうえで「うちはちょっとこうだから、こういう形にしたい」といった柔軟な取り組みが必要ではないかと思います。しかし、そこでうまく共通項を見出して、「じゃあ、こういうプログラムならみんなで参加しよう!」という形が作れれば、さらに面白いことができるのではないかと感じています。
蓜島 個社ごとに目的を大切にし、それをしっかり話し合ったうえで、手段が共通するのであれば一緒に取り組むということですね。
渡辺 まさにその形がうまく機能すれば、プロジェクトとして立ち上がると思います。今はちょうど良いタイミングでもありますし、私たちも「やってみよう」と思えれば、そうした柔軟な取り組みもできると思うので、とても面白いことだと思います。
渡辺 そうですね、他社との交流が盛んな会社と、そうでない閉鎖的な会社があって、成長のスピードに差が出てくるのではないかと思います。
蓜島 渡辺さんは、ご自身が参加された越境プログラムに参加した時のネットワークは続いていますか?
渡辺 一部続いています。全員ではありませんが、転職後もそのつながりがきっかけで、ヒアリングに伺ったこともあります。
蓜島 もう何十年も経っていますよね?
渡辺 当時お世話になった方で、お酒をご一緒したこともある方に、ちょっとヒアリングしてみたいと思ったことがありました。名刺をひっくり返してなんとか連絡先をたどり、繋いでもらって、ヒアリングに伺いました。
蓜島 同志のような、仲間がいる感じですかね。
渡辺 そうですね。私が参加者側だった時は、人事になる前で、開発やマーケティング、企画を担当していました。しかし、人事に移ってからは、久しぶりに人事部門にいた方とコンタクトを取ってヒアリングできたので、その点は良かったですね。
蓜島 ネットワーキングを進める際、実際にそれを企画する過程での難しさや、想定される障壁にはどのようなものが考えられるでしょうか?
渡辺 それは会社によると思いますが、企画を始める前の、社内の決裁を通すのがハードルが高いのではないでしょうか。当然、「何のためにやるのか」という目的が大前提だと思います。それがしっかりと説明できるかどうかが大きなポイントです。手段から入ると難しいと思います。確かに越境というやり方は、方法や手段の一つではありますが、それはあくまでツールや方法論に過ぎません。ここから入ってしまうと、どうやってやるか(How)思考になってしまうので、まずは「何のためにやるのか」が先にあるべきです。
そして、越境がちょうどよくオプションとして繋がるように構成できれば理想的ですが、会社によっては、人事の方々がそこまで話を持っていくのが難しい場合もあるようです。そのような文化や慣習があることも考慮しなければならないでしょうし、さまざまな事情もあると思います。そうした点は、ハードルになるかもしれませんね。
蓜島 何社かが集まると、それぞれの会社には異なる目的がありますよね。そのため、1つの目的で1つのイベントを開催するのは難しいですよね。
渡辺 ですので、やはりそういった場を作って、色々な企業がどんな悩みを抱えているのか、特に人事の方々がどんな困りごとを持っているのかを出し合い、議論するのは非常に有意義で興味深いと思います。企業ごとに悩み事は異なり、それこそ多様性だと思うんです。人事の困りごとは様々だと思います。だから、一つのプログラムにみんなで参加するというよりは、それぞれの企業に固有の事情があるので、そういった点も踏まえたうえで「うちはちょっとこうだから、こういう形にしたい」といった柔軟な取り組みが必要ではないかと思います。しかし、そこでうまく共通項を見出して、「じゃあ、こういうプログラムならみんなで参加しよう!」という形が作れれば、さらに面白いことができるのではないかと感じています。
蓜島 個社ごとに目的を大切にし、それをしっかり話し合ったうえで、手段が共通するのであれば一緒に取り組むということですね。
渡辺 まさにその形がうまく機能すれば、プロジェクトとして立ち上がると思います。今はちょうど良いタイミングでもありますし、私たちも「やってみよう」と思えれば、そうした柔軟な取り組みもできると思うので、とても面白いことだと思います。

(写真は左から渡辺氏、高橋氏)
高橋さん(以下、高橋) 本質的には越境自体は手段に過ぎないので、体験する価値をどのように会社で活かしていくかが大切なポイントだと思います。昨年、当社主催でプロボノに送り出している人事の方を集めて会議を行ったのですが、今のような話題もあがりました。先ほど蓜島さんがおっしゃったように、結局手段はみんな同じでいいですよね、で落ち着いていました。また、「どうしたら上司に承認してもらえるか」という話題もあがりました。そこには、効果の測定や、それをどれだけ可視化できるか、という問題も関係しているんだと思います。
蓜島 そうすると、自律的に「目的はこうで、手段はこうで、期待される効果はこうですよ」といった形で進めるよりも、お二人の話を聞いていると、そもそも「うちの目的はこうなんだけど、どうやろうか?」という議論を、あるネットワークの中で進めていく過程があって、最終的に「じゃあ、こういう手段を一緒にやらない?」という形で動き出すような流れになるんですね。
高橋 そうですね。プロボノは、元々ミドルシニア層の方々がメインターゲットでした。一社で長く働いている方々が外で体験することで、自分のパーソナルスキルは何かを見つけ、それが外に目を向けるきっかけになることを期待してスタートしたので、そのような評価基準で評価していきました。しかし、最近は評価軸が変わってきています。そういった変化を経て、自分たちはどうやってオープンイノベーションを進め、他の会社と連携しながら仕事を進めていくのか、また、ベンチャーの力をうまく活用していくのか、そのためにベンチャーとどう付き合うべきか、といったことが重要になっています。会社ごとに目的が変わっているので、評価軸はそれぞれの会社に合わせて少しずつ調整しながら運営しているところです。
蓜島 同じ手段で同じことをやっているように見えますが、一人一人が持ち帰ってくるものが変わるということですね。
渡辺 目的が違うと持ち帰るものも異なるということでしょうね。
蓜島 ということは、その後のフォローアップが大事ということですか?
渡辺 それも多様性だと思います。手段だけは共通でいいというのはあったとしても、その会社ごとに利用する意図が違っているのは当たり前ですよね。先ほどの効果測定の仕方は、目的が違えば評価軸も違うでしょうから。
蓜島 色々な人事のネットワークがありますが、そういうところから一緒に議論ができるような仲間探しもしないといけないですね。
蓜島 そうすると、自律的に「目的はこうで、手段はこうで、期待される効果はこうですよ」といった形で進めるよりも、お二人の話を聞いていると、そもそも「うちの目的はこうなんだけど、どうやろうか?」という議論を、あるネットワークの中で進めていく過程があって、最終的に「じゃあ、こういう手段を一緒にやらない?」という形で動き出すような流れになるんですね。
高橋 そうですね。プロボノは、元々ミドルシニア層の方々がメインターゲットでした。一社で長く働いている方々が外で体験することで、自分のパーソナルスキルは何かを見つけ、それが外に目を向けるきっかけになることを期待してスタートしたので、そのような評価基準で評価していきました。しかし、最近は評価軸が変わってきています。そういった変化を経て、自分たちはどうやってオープンイノベーションを進め、他の会社と連携しながら仕事を進めていくのか、また、ベンチャーの力をうまく活用していくのか、そのためにベンチャーとどう付き合うべきか、といったことが重要になっています。会社ごとに目的が変わっているので、評価軸はそれぞれの会社に合わせて少しずつ調整しながら運営しているところです。
蓜島 同じ手段で同じことをやっているように見えますが、一人一人が持ち帰ってくるものが変わるということですね。
渡辺 目的が違うと持ち帰るものも異なるということでしょうね。
蓜島 ということは、その後のフォローアップが大事ということですか?
渡辺 それも多様性だと思います。手段だけは共通でいいというのはあったとしても、その会社ごとに利用する意図が違っているのは当たり前ですよね。先ほどの効果測定の仕方は、目的が違えば評価軸も違うでしょうから。
蓜島 色々な人事のネットワークがありますが、そういうところから一緒に議論ができるような仲間探しもしないといけないですね。

(写真は左から蓜島氏、渡辺氏)
渡辺 そうですね、そういう方々と議論したいですね。私はなるべく外に出て交流するようにしているのですが、人事の方々は何か困っていることはあるのかな、と感じることがあります。自分はこうしているけれど、他の人はどうなんだろう、と思うこともあります。
蓜島 そうした現場の声や迷いを受け止める仕組みとして、管理職になる前の段階から選択の機会を提供できるような企画があれば、面白いですね。
渡辺 そうですね、面白いですよね。私が過去に参加した越境プログラムは、管理職になった直後に参加したんです。その時、もっと若いうちに参加できていたら、もっと違ったんじゃないかと思いました。先ほど申し上げた都築電気で実施した越境プログラムについては、若手向けのライトプランと、管理職向けの重ためのプランで分けましたが、それは良かったと思います。ライトプランには20代の若手社員から手が挙がってきましたし、重ためのプランは管理職が多く手を挙げました。そのように重たさを分けて企画するということもできますが、多様性を感じてもらおうと思っていたので、元々線を引くつもりは全くありませんでした。
蓜島 そうした現場の声や迷いを受け止める仕組みとして、管理職になる前の段階から選択の機会を提供できるような企画があれば、面白いですね。
渡辺 そうですね、面白いですよね。私が過去に参加した越境プログラムは、管理職になった直後に参加したんです。その時、もっと若いうちに参加できていたら、もっと違ったんじゃないかと思いました。先ほど申し上げた都築電気で実施した越境プログラムについては、若手向けのライトプランと、管理職向けの重ためのプランで分けましたが、それは良かったと思います。ライトプランには20代の若手社員から手が挙がってきましたし、重ためのプランは管理職が多く手を挙げました。そのように重たさを分けて企画するということもできますが、多様性を感じてもらおうと思っていたので、元々線を引くつもりは全くありませんでした。
会社の枠を越えた人材育成
高橋 越境した人材は、やはりその経験が大きなモチベーションとなり、仕事に対して非常にプラスの影響を与えると思います。そういった人材を組織としてどう生かしていくかですよね。当社の他社留学経験者による卒業生コミュニティがあるのですが、勉強会をすると非常に熱い議論をするんです。異なる会社の人たちではありますが、共通の経験を持つ同志として、お互いに「こんなことに悩んでいる」ということを共有し、みんなで相談し合っています。また、他社留学を積極的に活用している企業の卒業生同士による飲み会に参加させていただく機会がありました。そこでは、「どうやって自分たちの会社を変えていくか」について、熱い議論が交わされていました。こうした意欲を持った人材を、いかに組織として活かしていくか―組織開発の視点でしっかりと考える必要があると強く感じました。
さらに、最近、現在留学している人たちの上司とのコミュニケーションが増えています。上司がこの時代にどのように部下を育てるか悩んでいて、育成する側としての難しさもあるようです。当社の場合、人材育成・開発のプロが伴走者として留学期間中、継続的に留学生のフォローを行います。越境経験を通じて、第三者の伴走者がいることで、その視点があるからこそ、気軽に言いやすくなることもあります。そうした関係を通じて、人材をどう育成していくかという、新しい人材育成のあり方が形になりつつあると感じています。
蓜島 最近では、ダイバーシティの観点から見ると、他者がメンターとなり、企業の枠を越えた人材育成が求められるようになっていますよね。
高橋 そうだと思います。ですので、一つ一つ人事とご相談しながら形にしていきたいです。せっかく外に出て貴重な経験をしたのに、そのまま何のフォローもなく放っておくのは、本当にもったいないですよね。
蓜島 どこの会社でも同じような課長研修をやっていることが多いですが、それだけではもったいないと感じます。その会社の戦略や人事制度にしっかりと絡めて、カスタマイズしますが、基本となる考え方としては、各社がそれぞれに閉じるのではなく、みんなで束になって、日本経済全体を活性化していこうという視点が必要だと思います。だからこそ、みんなで一緒に考えたいですね。
渡辺 これまで日本企業は、ずっと一社ごとに個別に研修を行ってきました。3社くらいが集まって、同じような等級やグレードの人たち同士でディスカッションをしたり、「ワイガヤ」的に意見交換する場があっても良かったんじゃないかと思うんです。
蓜島 各社で権限規定が異なるからこそ、その延長線上にある研修も会社ごとにバラバラになってしまっているんですよね。
渡辺 現場では、思考停止に近い状態で、とにかく決まった研修を回すことに手一杯になってしまっていて、「変える」余地がなかなか持てていない人事もいますよね。
高橋 各社とも研修のロジックが非常によく構築されていますよね。ただ、毎年同じことを繰り返していくだけで、本当にこれでいいのか?とモヤモヤしている人事の方もいます。そのモヤモヤをみんなで交流しながら、既存の枠を壊す―そういう動きが、求められているんじゃないでしょうか。
さらに、最近、現在留学している人たちの上司とのコミュニケーションが増えています。上司がこの時代にどのように部下を育てるか悩んでいて、育成する側としての難しさもあるようです。当社の場合、人材育成・開発のプロが伴走者として留学期間中、継続的に留学生のフォローを行います。越境経験を通じて、第三者の伴走者がいることで、その視点があるからこそ、気軽に言いやすくなることもあります。そうした関係を通じて、人材をどう育成していくかという、新しい人材育成のあり方が形になりつつあると感じています。
蓜島 最近では、ダイバーシティの観点から見ると、他者がメンターとなり、企業の枠を越えた人材育成が求められるようになっていますよね。
高橋 そうだと思います。ですので、一つ一つ人事とご相談しながら形にしていきたいです。せっかく外に出て貴重な経験をしたのに、そのまま何のフォローもなく放っておくのは、本当にもったいないですよね。
蓜島 どこの会社でも同じような課長研修をやっていることが多いですが、それだけではもったいないと感じます。その会社の戦略や人事制度にしっかりと絡めて、カスタマイズしますが、基本となる考え方としては、各社がそれぞれに閉じるのではなく、みんなで束になって、日本経済全体を活性化していこうという視点が必要だと思います。だからこそ、みんなで一緒に考えたいですね。
渡辺 これまで日本企業は、ずっと一社ごとに個別に研修を行ってきました。3社くらいが集まって、同じような等級やグレードの人たち同士でディスカッションをしたり、「ワイガヤ」的に意見交換する場があっても良かったんじゃないかと思うんです。
蓜島 各社で権限規定が異なるからこそ、その延長線上にある研修も会社ごとにバラバラになってしまっているんですよね。
渡辺 現場では、思考停止に近い状態で、とにかく決まった研修を回すことに手一杯になってしまっていて、「変える」余地がなかなか持てていない人事もいますよね。
高橋 各社とも研修のロジックが非常によく構築されていますよね。ただ、毎年同じことを繰り返していくだけで、本当にこれでいいのか?とモヤモヤしている人事の方もいます。そのモヤモヤをみんなで交流しながら、既存の枠を壊す―そういう動きが、求められているんじゃないでしょうか。
Part2はここまでとなります。次回は最終回となります。Part3では「越境研修と人事が果たすべき役割」についてお届けします。さらに充実した内容となっておりますので、ご期待ください!
▶Part3「越境研修と人事が果たすべき役割」 記事はこちら
